右四間飛車対策これまでのあらすじ
私のライバルは、近所の将棋クラブのおじさんです。かつては県代表の常連でした。
今困っていることは、私が振り飛車模様にした時に、右四間飛車ばかりやってくることです。
本当は向かい飛車をやりたいのですが、相手が飛車先を突いてこなければ出来ません。
おじさんとの勝率は2割くらいだと思いますが、対右四間に限れば、もっと下がります。
以前は他にも色々やってきたのですが、勝率の偏りを見て味をしめたと思われます。
向かい飛車以外では石田流三間飛車も指しますが、それらの戦法は自分から攻めることが出来ます。
右四間に対しては定跡通りの普通の四間飛車に組んでいますが、これはいつも指している振り飛車とは、かなり勝手が違います。
我流の仕掛けで暴れるのですが、うまくいきません。この記事を参照してください。
右四間飛車対策(左美濃から銀冠)を調べてみました
右四間の仕掛けは端に桂を跳ねて角をどかせる、というところから始まるのが普通ですが、おじさんとの試合ではそうはなりません。
いつも角頭を狙われます。▲5六銀が早いからこうなる、というところまでは調べました。

対右四間飛車の指す手のタイミングを調べて分かった!
それ以外にも▲7七角や▲5八金左、▲9八香なども指すタイミングがあるようです。
そして反撃手段も調べてみました。
まず私の昔覚えた右四間定跡は、端に桂馬を跳ねるというものでした。
7三へ跳ねるよりも隙が無くて、こちらの方がよいと思っていました。しかし一長一短のようです。おじさんは今のところ端には跳ねて来ないので、現時点では扱いません。
△7四歩型の長所を簡単にまとめると、

桂馬を跳ねる以外に、飛車を寄って相手の角頭を狙う手が生じる長所があります。
まさしくおじさんがやってくる手であります。
△7四歩を突かないと、相手に▲7五歩と伸ばされて、反撃の拠点にされることがあります。(銀を7六に移動する変化もあり、受けにきく形でもあります。)
右四間側が桂馬を端に跳ねるなら、振り飛車側は必ず7筋の歩を伸ばしておきたいと思いました。
右四間飛車超急戦に対する考え方
指すタイミングに気をつけるべき手を最初にいくつかあげましたが、どの手も私は早すぎるようです。
手順を調べず駒組の形だけ見て指しているから、相手にその隙を突かれるわけです。
相手の歩が6四まで伸びていて、いつでも△6五歩がある形だと、ことなかれ主義で▲5六銀や▲7七角を安直に指してしまっていました。
しかし桂馬が参加しない攻めは、おそれるべきではないと思いなおしました。単純な△6五歩は、これからはしっかりとがめる覚悟を持って指そうと思います。

右四間飛車対策▲5六銀や▲7七角のタイミング
それは、右四間側が△7三桂と跳ねてからです。
そうすれば△7二飛とは指しにくくなるからです。(そもそも銀や角は、その位置までずっと移動させないという指し方もあります。)
右四間飛車対策▲9八香のタイミング
これは相手の角を空成りにする狙いがあります。
△6五歩の時点では遅いと思いますし、▲7七角より先に指すのは早いでしょう。
右四間飛車対策▲5八金左のタイミング
これも何も考えず、早いうちから指すと損します。
今回調べて分かりましたが、ギリギリまで5九の位置でひっぱるべきだと思いました。
ひとつは速攻で仕掛けられた場合、
角を成られると桂アタリになりますが、▲7九金とヒモをつけて受けることが出来ます。
こういう手はあまり好きではないのですが、金上りを急ぐ理由はないというのは十分納得できました。
もうひとつは、金上りを保留すると、飛車を右辺に展開する余地を残せるということです。
穴熊に組まれそうな場合、5六の銀と協力して反撃することが出来ます。
▲5八金左は、一番最後に指す手になるでしょう。
右四間飛車対策▲4六歩
この手にも触れておきます。
この手は穴熊に組まれそうになった場合、▲4五銀とぶつけるための支えとなります。
もちろんおなじみの美濃囲いに対する、角と桂馬を使った寄せを消す狙いもあります。
右四間飛車対策の手の指す順序まとめ
1.▲7七角
2.▲9八香
3.▲5六銀
4.▲4六歩
5.▲5八金左
となります。
3の▲5六銀は、相手に応じて選択することになります。反撃する手が生じるかもしれません。それが無理なら▲5六銀へ移行すればよいでしょう。
右四間飛車対策▲5六銀の狙い
昔の定跡で感じていたことは、
右四間側の腰掛銀と見合いになっているのだろう、
ということでした。
歩越し銀が向かい合う局面は、将棋のあらゆる戦型に現れます。これがバランスを取る形なのだと、漠然と思っていました。
ほかの戦型は分かりませんが、今回扱っている四間対右四間における▲5六銀は、意外なほどに幅広く機能する位置であると分かりました。
まず、普通の△6五歩の仕掛けに対しては、定跡では▲同歩ではなく▲同銀と指すことになっています。
ここでは銀を捌くべきだということなのでしょう。
5六に位置する銀は、右側にも機能します。
少し触れましたが、穴熊に組まれそうな場合に▲4六歩で支えの準備をした後、▲4五銀とぶつけることが出来ます。
急戦なら左辺に、持久戦なら右辺に働く柔軟さがすばらしいと思います。
もうひとつ、おじさんがやってくる左美濃から銀冠へ組む手順に対して、こちらは▲4七銀と引きます。
これはダイヤモンド美濃という囲いです。
このあと▲7八飛から捌くという感じで指します。
これだけ勉強すれば、対おじさんの当面の対策としては十分でしょう。よいご報告ができるよう、頑張ってきます。

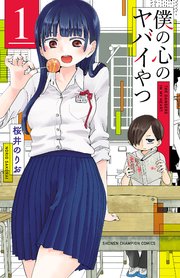

コメント